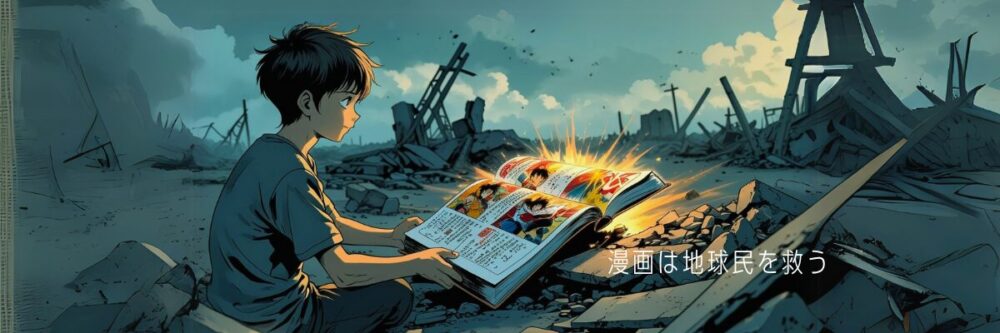自分の将来や夢、友達との関係で悩んでいた青春時代。夢中になって読んでいたバレエ漫画を思い出して、とても読みたくなってこのページおいでいただいた方が多いと思います。
貧しくも心豊かだった昭和と言われる時代に生まれたバレエ漫画の数々。調べてみたら、本当にすべての作品がキラキラしていて、ほとばしる情熱と生きる力を感じました。
改めて、本当に良い時代だったんなあと感動しました。
そんな昭和のバレエ漫画について、時代の状況と合わせて70年代80年90年代に発表されたバレエ漫画を振り返りっていきたいと思います。
そして、うれしいことに復刻版として現代に蘇った作品のご紹介もして参りますので、最後まで、お付き合いください。
- 海外からキングダムを無料で読もうとすると、ウイルス感染や個人情報流出などの危険を伴う違法サイトに行き着く可能性がある
- 違法サイトでのダウンロードは法的な処罰の対象となるリスクがあること
- 漫画村のようなサイトは閉鎖されたが、海外には依然として海賊版サイトが多く存在し、いたちごっこが続いている現状
- 正規のサービスではキングダムを全巻無料で読むことはできないが、初回特典やキャンペーンを利用してお得に読む方法があること法
夢と憧憬!昭和の「バレエ 漫画」の世界
昭和の少女たちの心を掴んだバレエ漫画とは

昭和の時代、バレエ漫画は少女たちの心を捉え、夢と憧れを与える存在でした。
戦後、家族を失った少女たちの感情に寄り添う「悲しい母娘もの」にバレエの要素が加わることで、一層人気を集めました。
初期の作品では、困難な状況に置かれた主人公がバレエを通して成長していく姿が描かれました。
『バレエ星』の主人公かすみは、病気の母を助けながらバレリーナを目指し、滝修行やバケツを使った特訓といった超展開な物語が読者を惹きつけました。
牧美也子先生の『マキの口笛』は、少女漫画における最初のバレエ漫画のヒット作と言えるでしょう。バレリーナを目指すマキの物語は共感を呼び、特にその可愛らしい衣装は少女たちの憧れの的となり、ファッションとしても注目されました。
このように、初期のバレエ漫画は、悲しい物語の中にバレエの美しさを描き出し、少女たちの夢を育みました。
時代が進むにつれて、谷ゆき子先生のような、超展開なストーリーと美しい絵柄で人気を博す作家も現れました。『まりもの星』では、予測不可能な展開や個性的なキャラクターが、少女たちにとって日常を忘れさせる魅力となりました。
昭和のバレエ漫画は、時代背景や少女たちの憧れを反映しながら、多様なスタイルで少女たちの心を捉えていったのです。登場人物の可愛らしいバレエの衣装やポーズを描くために、スタイル画や二段、三段ぶち抜きの表現方法が確立されたことも、このジャンルの功績として挙げられます。
なぜ昔の少女たちはバレエ漫画に夢中になったのか?

まず、終戦後、日本にバレエ文化が 浸透し始めた時期であり、1950年の映画『赤い靴』の公開や「白鳥の湖」の日本初公演などがきっかけとなり、バレエは多くの人々の目に触れ、特に少女たちの心を惹きつけました。
バレエが持つロマンティックなイメージも、少女たちが夢中になった大きな理由の一つです。
美しい衣装、トゥシューズ、お姫様のような主役、そして感動的な音楽と物語は、少女たちの憧れと理想を象徴していました。日常生活では触れる機会の少ない華やかで夢のような世界が、バレエ漫画を通して身近に感じられたのです。
また、当時の少女漫画の主流であった「悲しい母娘もの」というジャンルとバレエが結びつくことで、感情的な共感を呼びました。困難な状況でもバレエに情熱を燃やし努力する主人公の姿は、少女たちに勇気や希望を与えました。バレエが「習い事」として日本で普及していたことも、バレエ漫画が受け入れやすかった要因です。
海外とは異なり、日本でバレエは比較的気軽に始められる習い事であったため、多くの少女たちがバレエ漫画の世界に共感し、親近感を抱きました。
さらに、牧美也子先生をはじめとする女性漫画家たちが、自身の憧れや美意識を込めて描いた美しい絵柄も、少女たちの心を強く惹きつけました。特に、可愛らしい衣装や繊細な装飾は、少女たちのファッションへの関心を刺激し、憧れの対象となりました。
このように、バレエの持つ夢のような魅力、物語の感動的な展開、そして美しい絵柄が組み合わさり、昔の少女たちはバレエ漫画の世界に深く魅了されたのです。
少女漫画雑誌「りぼん」を彩った昭和のバレエ作品

昭和の少女漫画雑誌「りぼん」では、少女たちの夢を育む多くのバレエ作品が掲載されました。
「りぼん」のバレエ漫画は、美しいバレエの描写に加え、主人公たちの成長、友情、恋愛といった要素が描かれ、読者の共感を呼びました。
牧美也子先生の『マキの口笛』は、「りぼん」を代表するバレエ漫画の一つです。
1960年から連載されたこの作品は、バレリーナを目指すマキの努力と成長を描き、その繊細で可愛らしい絵柄、華麗なバレエシーン、そしておしゃれな衣装は少女たちの憧れとなりました。特に衣装の人気は高く、プレゼント企画が行われたほどです。『マキの口笛』は、少女漫画における本格的なバレエ漫画の先駆けとして、ジャンル確立に大きく貢献しました。
また、山岸凉子先生の『アラベスク』も「りぼん」を代表する作品です。
1971年より連載された『アラベスク』は、バレエの世界の厳しさや美しさ、ダンサーの心理描写を深く描き出し、少女漫画の表現を広げました。単なる美しい習い事としてではない、芸術としてのバレエのリアリティを描いた点が画期的であり、多くの読者に感動を与え、高い評価を得ました。
このように、「りぼん」は昭和の時代、牧美也子先生や山岸凉子先生といった才能ある作家たちによって、少女たちの夢と憧れを映し出す魅力的なバレエ漫画の世界を提供し続けたのです。
「なかよし バレエ 漫画」など、学年誌での展開

昭和の時代、少女漫画は少女たちの夢と憧れを映し出す鏡であり、バレエ漫画はその中でも特別な輝きを放っていました。「小学一年生」や「小学二年生」といった学年誌は、少女たちが初めて漫画に触れ、バレエ漫画を通して夢を育む重要な場所でした。谷ゆき子先生のように、約10年もの間バレエ漫画のシリーズを連載し、圧倒的な人気を博した漫画家も存在しました。
学年誌のバレエ漫画の特徴は、子供たちの読者層を強く意識した親しみやすいストーリー展開です。谷ゆき子先生の『まりもの星』では、突然チュチュ姿に変身する母親や、断崖絶壁での特訓、へび岩のたたりなど、予測不能な超展開が繰り広げられました。このような奇想天外な物語は、子供たちの想像力を刺激し、「次号はどうなるのか」と読者を惹きつけました。日常からかけ離れたスリリングな展開は、子供たちにとって大きなエンターテイメントとして楽しまれたのです。
学年誌ならではの要素として、連載当時の雑誌の雰囲気をそのまま伝える復刻版も存在します。『まりもの星 [完全復刻・超展開バレエマンガ]』のように、編集者の煽り文句や小さな読者の投稿欄なども収録されており、当時の熱気や読者の反応を追体験できます。これは、当時読んでいた読者には懐かしい思い出を呼び起こし、初めて読む読者には、当時の少女たちがどのような点に夢中になっていたのかを知る貴重な機会となります。
さらに、学年誌のバレエ漫画は、絵柄の美しさも重視されていました。谷ゆき子先生が描く少女たちのキラキラとした瞳や、繊細なバレエの衣装は、少女たちの憧れを象徴していました。このように、学年誌のバレエ漫画は、子供たちの夢を育み、想像力を刺激する魅力的なコンテンツとして、多くの少女たちの心を捉えていたのです。
金字塔となった「アラベスク」の衝撃

現在のバレエ漫画界においても、山岸凉子先生の「アラベスク」は依然として特別な地位を占めています。1971年の連載開始以来、その芸術性の高さと、バレエへの深い洞察は色褪せることなく、新たな読者を魅了し続けています。
「アラベスク」が描いた、ダンサーの肉体的・精神的な苦悩、舞台にかける情熱、そして芸術至上主義は、単なる少女漫画の枠を超え、普遍的な人間ドラマとして読み継がれています。バレエの技術的な描写のリアリティは、現代の読者にとっても新鮮であり、バレエの世界への興味を引き込む力を持っています。
また、「アラベスク」が少女漫画におけるバレエ漫画のコンセプトを変革した功績は大きく、その影響は現代のバレエ漫画にも色濃く見られます。感情や葛藤を深く描き出す手法、芸術性の高いレベルの追求は、多くの後続の作家たちに受け継がれ、より多様で深みのあるバレエ漫画が生まれる土壌となりました。
復刻版や電子書籍版の刊行などを通して、現代の読者が容易に「アラベスク」に触れることができる環境も、その影響力を保ち続けている要因の一つです。過去の作品として懐かしむだけでなく、その芸術的な価値と普遍的なテーマは、現代の読者にとっても新たな発見と感動を与え続けているのです。
このように、「アラベスク」は、連載から半世紀以上を経た今もなお、バレエ漫画の金字塔として輝きを放ち、その芸術性の高さと深い 粗筋によって、時代を超えて読み継がれるべき作品として、その存在感を増しています。
昭和のバレエ漫画に見るヒロインたちの葛藤と成長

昭和のバレエ漫画は、単に華麗な舞台を描くのではなく、バレリーナを目指すヒロインたちの内面的な葛藤と成長を描いてきました。
黎明期には、牧美也子先生の作品のように「悲しい母娘もの」を基盤に、主人公が困難を乗り越え自立する姿が描かれました。
1970年代に入ると、谷ゆき子先生の『バレエ星』のような予測不能な超展開の中で、ヒロインが数々の試練に立ち向かい成長する物語が登場しました。同時期には、山岸凉子先生の『アラベスク』のように、才能を持ちながらも努力と苦悩を通して成長していく本格的なバレエ漫画も現れました。
1980年代以降には、水沢めぐみ先生の『トウ・シューズ』のように、等身大のヒロインがコンプレックスや悩みを抱えながらも、周囲の支えや自身の努力で成長していく物語も描かれるようになりました。
これらの作品に共通するのは、バレエへの情熱がヒロインたちの成長の大きな原動力となり、読者に夢と勇気を与えたことです。
絵柄で振り返る!昭和のバレエ漫画の変遷
「一覧 70年代」:情熱と涙の物語
1970年代は、日本のバレエ漫画の世界において、情熱と涙が色濃く描かれた、まさに物語が花開いた時代と言えるでしょう。
「図書の家」のバレエ漫画リストを見ると、少女たちのひたむきな情熱、夢に向かう中で流される涙、そしてその先に掴み取る成長が、多様な作品群を通して描き出されていたことが伺えます。この時代は、少女たちがバレエという芸術に抱く憧憬と、それに伴う苦悩や努力が、漫画という形で共感を呼び、多くの読者の心を捉えたのです。
| No | 年 | 作品名 | 作者 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | アラベスク | 山岸凉子 | バレエの芸術と成長を描く |
| 2 | 1970 | さよなら星 | 谷ゆき子 | 超展開、困難乗り越え成長 |
| 3 | 1970 | アコとミドリ | 北島洋子 | |
| 4 | 1970 | ふたつ星 | 谷ゆき子 | |
| 5 | 1970 | 信じていたのに | 丸田信子 | |
| 6 | 1970 | 真由子の日記 | 大和和紀 | バレエをきっかけに立ち直る青春 |
| 7 | 1971 | かあさん星 | 谷ゆき子 | 学年誌で連載 |
| 8 | 1971 | 白鳥はかえらない | 河合秀和 | |
| 9 | 1971 | ほしのバレリーナ | 谷ゆき子 | 幼稚園で連載 |
| 10 | 1971 | 永遠のオーロラ | 上原きみ子 | 情熱と成長を描く |
| 11 | 1972 | まりもの星 | 谷ゆき子 | 奇想天外な展開と情熱 |
| 12 | 1972 | きょうだい星 | 平田真貴子 | |
| 13 | 1972 | あこがれの旋風(かぜ) | すずき真弓 | |
| 14 | 1972 | 白鳥の歌をきいて! | 有吉京子 | デビュー作 |
| 15 | 1972 | 赤い靴 | すずき真弓 | テレビドラマタイアップ |
| 16 | 1972 | 赤い靴 | 奥村真理子 | テレビドラマタイアップ |
| 17 | 1972 | 赤い靴 | 飛鳥幸子 | テレビドラマタイアップ |
| 18 | 1972 | 赤い靴 | 森由岐子 | テレビドラマタイアップ |
| 19 | 1972 | 赤い靴 | 美鈴緑 | テレビドラマタイアップ |
| 20 | 1973 | バレリーナの星 | 谷ゆき子 | 学年誌で連載 |
| 21 | 1973 | 悲しみのチュチュ | 田中雅子 | |
| 22 | 1973 | 赤い靴 | 原田千代子 | テレビドラマタイアップ |
| 23 | 1973 | 赤い靴 | 奥村真理子 | テレビドラマタイアップ |
| 24 | 1973 | 赤い靴 | 飛鳥幸子 | テレビドラマタイアップ |
| 25 | 1973 | 赤い靴 | 森由岐子 | テレビドラマタイアップ |
| 26 | 1973 | 黒いひとみのアヒルの子 | 岡元敦子 | デビュー作 |
| 27 | 1974 | ママの星 | 谷ゆき子 | 学年誌で連載 |
| 28 | 1974 | ガラスの靴 | 飛鳥幸子 | 学年誌で長期連載 |
| 29 | 1974 | アラベスク 第二部 | 山岸凉子 | 更なる才能開花と苦悩 |
| 30 | 1974 | にじのバレリーナ | 谷ゆき子 | 幼稚園で連載 |
| 31 | 1975 | アマリリスの星 | 谷ゆき子 | 学年誌で連載 |
| 32 | 1975 | のろいのトゥ・シューズ | 谷ゆき子 | ホラー、「まりもの星」に収録 |
| 33 | 1976 | SWAN -白鳥- | 有吉京子 | バレエに情熱を燃やす少女たち |
| 34 | 1976 | 白鳥ののろい | 谷ゆき子、山崎巌 | ホラー、「まりもの星」に収録 |
| 35 | 1977 | 舞子の詩 | 上原きみ子 | 「ちゃお」で長期連載 |
この年代の特筆すべき作品の一つに、山岸凉子先生の『アラベスク』 が挙げられます。
『りぼん』 で1971年から連載を開始したこの作品は、それまでのバレエ漫画とは一線を画し、バレエの芸術性や身体表現に深く焦点を当て、一石を投じたエポックメイキングな作品 でした。主人公の織田亜夜子が、その才能を開花させ、プロのバレリーナとして成長していく過程は、単なる夢物語ではなく、厳しいレッスンや人間関係、精神的な葛藤 を通して描かれました。読者は、亜夜子の情熱と、その裏にある努力や苦悩に共感し、共に涙し、成長を見守ったのです。
また、1960年代から引き続き、谷ゆき子先生も学年誌を中心に精力的にバレエ漫画を発表していました。 『さよなら星』、『かあさん星』、『まりもの星』 など、その超展開な物語 は、子供たちに夢を与えつつも、主人公たちが直面する数々の困難を通して、決して平坦ではない成長の道を示唆していました。

例えば、『まりもの星』では、突然チュチュ姿で現れる母親や、崖での特訓といった奇想天外な展開 の裏で、主人公の”まりも”がバレエに懸ける情熱や、様々な試練に立ち向かう姿が描かれ、読者はその予測不能な物語 に夢中になりながら、彼女の成長を見守ったのです。
さらに、この時代には、上原きみ子先生の『永遠のオーロラ』 や、有吉京子先生のデビュー作である『白鳥の歌をきいて!』 など、新たな才能も登場し、バレエ漫画の世界に新たな風を吹き込みました。これらの作品もまた、主人公たちのバレエへの情熱、ライバルとの競争、そして舞台にかける涙と努力を通して、少女たちの成長を描き出しています。
1972年には、テレビドラマ『赤い靴』とのタイアップ企画 として、複数の作家がそれぞれの学年誌で同名の漫画を連載するという、メディアミックスの動きも見られました。これは、バレエというテーマが、単なる漫画のジャンルを超え、より広い層の読者に影響を与えるほどに浸透していたことを示しています。それぞれの『赤い靴』で描かれた少女たちの、バレエへの憧れ、挫折、そして再び立ち上がる姿は、多くの子供たちの心を熱くしました。
どの作品にも共通するのは、バレエに情熱を燃やす少女たちの姿と、その情熱ゆえに流される喜びや悲しみの涙、そして困難を乗り越えていく成長の物語です。1970年代のバレエ漫画は、まさに少女たちの夢と希望、そして時には挫折や苦悩を描き出し、読者の心に深く刻まれる、情熱と涙の物語で彩られた時代だったと言えるでしょう。
「一覧 80年代」:恋愛要素の強まり
1980年代のバレエ漫画は、少女漫画全体の黄金期を背景に、恋愛要素が重要な鍵となりました。「図書の家」のリストからも、本格的なバレエ物語に恋愛が色濃く加わり、夢と恋に揺れ動く主人公たちの成長が描かれる傾向が顕著です。
| No | 年 | 作品名 | 作者 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 白鳥のソナタ | 聖悠紀 | バレエに打ち込む少女たちの友情とライバル関係、そして成長を描く |
| 2 | 1980 | くるみ割り人形 | 北島洋子 | クリスマスの夜に起こる、くるみ割り人形とねずみ王の戦いを描いたバレエ作品の漫画化 |
| 3 | 1981 | Lady Love | 小野弥夢 | バレエに夢見る少女レディが、恋とライバルとの出会いを通して成長する物語 |
| 4 | 1981 | パステル気分 | パステル気分 | チアリーディングに情熱を燃やす少女が、バレエの経験を通して成長していく青春物語 |
| 5 | 1982 | 夢みるバレリーナ | 牧野和子 | バレリーナを目指す少女のひたむきな努力と成長を描く |
| 6 | 1982 | 銀の星・金(ゴールド)の星 | 和田慎二 | バレエに魅せられた双子の少女たちが、それぞれの才能を開花させていくドラマ |
| 7 | 1983 | 星のデジャヴ | 橋千鶴 | バレエの才能を持つ少女が、過去の記憶と向き合いながら成長していく物語 |
| 8 | 1983 | ティアラ・レッスン | 藤田和子 | バレエ教室を舞台に、少女たちの友情や努力、そして恋を描く |
| 9 | 1983 | NY小町 | 吉田秋生 | ニューヨークを舞台に、バレエダンサーを目指す少女の生活と恋愛を描く |
| 10 | 1984 | シャーロットの贈り物 | 北島洋子 | 少女と子豚の友情を描いた物語をバレエで表現することを目指す少女たちの物語 |
| 11 | 1985 | シンデレラ・ワルツ | 聖悠紀 | シンデレラを題材にしたバレエに挑む少女たちの努力と友情を描く |
| 12 | 1986 | 星のオルゴール | あさぎり夕 | バレエと音楽に情熱を燃やす少女たちの青春を描く |
| 13 | 1986 | スチュワーデス物語 | 上原きみ子 | スチュワーデスを目指す主人公が、バレエの経験を生かして困難を乗り越えていく物語(バレエ要素は一部) |
| 14 | 1987 | SWAN -白鳥- | 有吉京子 | バレエに生きる少女たちの才能、努力、愛憎が絡み合う本格的なバレエドラマ |
| 15 | 1988 | フラワー・フェスティバル | 萩尾望都 | ロンドンのバレエ学校サマーキャンプを舞台に、少女みどりの恋と成長を描く |
| 16 | 1988 | バレリーナはア・ラ・カルト | 柴田昌弘 | バレエをテーマにした短編集 |
| 17 | 1989 | 夢みるトーション | 川原由美子 | 体操部に所属する少女が、バレエの動きを取り入れて成長していくスポ根コメディ(バレエ要素あり) |
萩尾望都先生の『フラワー・フェスティバル』は、ロンドンのサマーキャンプを舞台に、義理の兄への恋心を抱くみどりの経験を描き、限られた時間の中で感情の動きやバレエを通じた成長を繊細に表現。恋愛とバレエが美しく織り交ぜられています。
有吉京子先生の『SWAN -白鳥-』は、70年代から続く人気作ながら、80年代も本格的なバレエストーリーと複雑な人間関係、恋愛模様で読者を魅了。才能ある主人公たちが、競争や恋愛を通して成長するドラマチックな展開が特徴です。
また、『星のデジャヴ』や『NY小町』など、海外を舞台にした国際色豊かな恋愛とバレエの物語も登場し始めました。異文化の中でバレエに挑戦し、異性との出会いや別れを経験する主人公たちの姿は、新たな視点を与えました。
一方、バレエ漫画全体の作品数は減少傾向にありましたが、フィギュアスケートや社交ダンスといった、バレエを源流とするダンスジャンルの漫画が増加。これらの作品でも、情熱、努力、そして恋愛は物語の重要な軸でした。
このように80年代のバレエ漫画は、恋愛要素を積極的に取り込み、主人公たちの感情や人間関係を深く描くことで、少女読者の共感を呼び、新たな魅力を開花させました。バレエの美しさと共に、甘く切ない恋の物語が描かれることで、バレエ漫画はより身近な存在として少女たちの心を捉え続けたのです。
「一覧 90年代」:多様化する表現
1990年代のバレエ漫画は、少女漫画市場全体の変化や若者文化の多様化を背景に、表現の幅を大きく広げた時代 と言えるでしょう。 「図書の家」のバレエ漫画リストを見ると、作品数は80年代に比べて減少傾向にあるものの、少女漫画という枠組みを超え、新たなジャンルや読者層に向けた多様なアプローチ が試みられたことが伺えます。
| No | 年 | 作品名 | 作者 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | あすなろ白書 | 柴門ふみ | 恋愛ドラマだが、ヒロインがバレエを習っている設定(バレエ要素は一部) |
| 3 | 1994 | 銀の爪 | 杉本亜未 | バレエ団を舞台にしたミステリー要素を含む作品 |
| 7 | 1997 | トウ・シューズ | 水沢めぐみ | 背の低いことがコンプレックスのくるみが、バレエを通して成長していく少女漫画の王道 |
| 9 | 1998 | レエ入門―俺がバレエを始めたわけ― | 徳弘雅也 | 少年誌で初めてバレエを本格的に取り上げたギャグ要素の強い読切作品 |
| 10 | 1998 | プリマでいこう! | さかたのり子 | 女性誌で連載された、バレリーナを目指す女性の仕事や生き方も描いた作品 |
| 11 | 1998 | 踊る王子様 | よしながふみ | BLを含む雑誌に掲載された、バレエをテーマにした短編作品(オムニバスの一作) |
この時期の特筆すべき作品の一つに、水沢めぐみ先生の『トウ・シューズ』 があります。19年間『りぼん』で作品を発表し続けていた水沢先生らしい、夢や目標に向かって前向きに頑張る主人公くるみの姿 を描いた本作は、少女漫画の王道 とも言える作品です。背の低いことがコンプレックスなくるみが、バレエを通して成長していく過程が、等身大の悩みや周囲の支え を交えながら描かれ、多くの少女読者の共感を呼びました。恋愛要素も描かれていますが、これまでのバレエ漫画とは異なり、悲しい展開や過酷な試練よりも、主人公のひたむきな努力と、周囲との温かい関係性 が中心に描かれている点が特徴的です。
また、90年代には、少年誌で初めて本格的にバレエを取り上げた作品として、徳弘雅也先生の読切『バレエ入門―俺がバレエを始めたわけ―』 (週刊少年ジャンプ)が登場しました。ギャグ要素の強い作品ではありますが、これまで少女漫画のイメージが強かったバレエというテーマが、少年漫画にも進出した ことは、表現の多様化を示す象徴的な出来事と言えるでしょう。
さらに、女性誌においても徐々にバレエ漫画が登場するようになり、さかたのり子先生の『プリマでいこう!』 (JOUR)などが連載を開始しました。これは、より成熟した読者層に向けた、恋愛だけでなく、仕事や生き方といったテーマも含むバレエ漫画 が求められ始めたことを示唆しています。
よしながふみ先生も、BLを含む多様なジャンルを扱う雑誌「Wings」で、『踊る王子様』 という短編を描いています。このように、特定のジャンルにとらわれない自由な表現 が、90年代のバレエ漫画に見られる傾向の一つと言えるでしょう。
一方で、『白鳥麗子でございます!』 のように、ギャグ漫画の中にバレエの要素が取り入れられたり、『とっても!ラッキーマン』 のように、ヒーロー漫画の一エピソードとしてバレエが登場したりと、既存のジャンルとバレエを組み合わせたユニークな作品 も見られます。これは、バレエという要素が、もはや特定の層の憧れだけでなく、幅広い層に親しまれる共通のモチーフ となりつつあったことを示しているのかもしれません。
90年代は、日本バレエ界において熊川哲也氏がローザンヌ国際コンクールで金賞を受賞し、プリンシパルに就任するなど、大きな進展があった時期でもありますが、バレエ漫画においては、量よりも質、そして多様な表現を模索する時代 であったと言えるでしょう。少女漫画の枠内での王道的な作品に加え、少年漫画や女性誌への進出、ギャグ漫画や他ジャンルとの融合など、様々な形でバレエが描かれるようになった ことは、2000年代以降のさらなるバレエ漫画の領域拡大への布石となったと言えるでしょう。
「平成」へと続く昭和バレエ漫画の系譜

昭和の時代、少女漫画においてバレエは重要なテーマの一つとして確立され、その流れは「平成」の時代へと確かに受け継がれていきました。
戦後の少女漫画黎明期には、戦災で家族を失った子供たちが多かった社会背景を受け、「悲しい母娘もの」の要素とバレエが結びついた物語が流行しました。この時期はバレエに関する資料も限られていたため、少女たちの感情や人間関係に焦点が当てられることが多かったと考えられます。しかし、バレエへの憧れは強く、それが漫画人気の背景にありました。
その後、牧美也子先生のような女性漫画家が登場し、バレエ漫画の世界に新たな展開をもたらします。「マキの口笛」は、可愛らしい絵柄や夢のようなバレエシーン、おしゃれなファッション描写で少女たちの心を掴み、少女漫画の表現に大きな影響を与えました。このように、視覚的な魅力が重視されるようになり、バレエは少女たちの憧れの的として、より鮮やかに描かれるようになります。
さらに、谷ゆき子先生は「バレエ星」や「まりもの星」といった作品で、予測不能な超展開という独自のスタイルを確立し、読者を飽きさせないエンターテイメント性を提供しました。『バレエ星』では、滝修行やバケツを持ってのターンの特訓、ダイナマイトによる爆破や狂犬に襲われるといった、バレエ漫画らしからぬ過激な展開が描かれ、当時の子供たちの注目を集めました。
そして、山岸凉子先生の「アラベスク」は、それまでのバレエ漫画とは一線を画し、バレエの芸術性や身体表現に深く焦点を当てた本格的な作品として登場します。
このように、昭和のバレエ漫画は、少女の夢や憧れを描きながらも、時代と共に多様な表現を獲得していきました。これらの作品が、「夢と希望」「努力と友情」「愛と葛藤」優雅さ、厳しさ、情熱を融合させ、後の平成以降の時代における多様なバレエ漫画へと繋がる系譜を築いたと言えるでしょう。
今なお輝く!昭和のバレエ漫画の魅力

昭和の時代に描かれたバレエ漫画は、時代を超えて今なお多くの読者を魅了し続けています。
その魅力の一つは、当時の少女たちの純粋な憧憬が色濃く反映されている点です。
煌びやかな衣装や優雅な舞いは、現代の読者にとっても、忘れかけていた夢や憧れを呼び覚ます力を持っています。特に、物が豊かではなかった時代において、バレエはまさに非日常の美しさを象徴しており、その強い輝きが作品を通して現代にまで伝わってくるのです。
また、昭和のバレエ漫画には、現代の作品にはあまり見られない独特のドラマ性があります。「悲しい母娘もの」に代表されるように、主人公が過酷な運命に翻弄されながらも、バレエへの情熱を失わずに立ち向かう姿は、読む者の心を強く揺さぶります。特に谷ゆき子の作品に見られるような、予想を裏切る「超展開」新鮮な驚きとして受け止められ、そのカオスな魅力に引き込まれるという声も少なくありません。
当時の読者が固唾を呑んで見守った、先の読めない物語の面白さは、今も色褪せることがありません。
さらに、牧美也子先生をはじめとする女性漫画家たちの描く美麗なイラストは、今見てもその輝きを失っていません。繊細な線で描かれたキャラクターたちの表情や、華やかで凝った衣装のデザインは、少女漫画ならではの美意識が凝縮されており、ファッションや美術的な観点からも十分に楽しむことができます。
そして、当時これらの漫画を読んでいた世代にとっては、懐かしさという特別な感情も魅力の一つです。子供の頃に夢中になって読んだ作品を再び手に取ることで、当時の記憶や感情が鮮やかに蘇り、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができます。
このように、昭和のバレエ漫画は、その時代ならではの純粋な憧れ、強いドラマ性、美麗な絵柄、そして懐かしさといった多層的な魅力によって、現代の読者をも惹きつけてやまないのです。それは、少女漫画の原点とも言える、普遍的な心の琴線に触れる力を持っているからに他なりません。
復刻版で再び出会える名作たち

上記「一覧 70年代」「一覧 80年代」「一覧 90年代」にご紹介しました全63作品のうち、現在までに復刻版が見られる書籍・ECサイトをご紹介します。試し読みができるサイトは「試読」マークをつけましたので、ご参考になれば幸いです。
| 作品名 | 作 者 | オリジナル イメージ画像 | コミック シーモア | ebook | ブック ライブ | book walker | Amazon | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラベスク | 山岸凉子 |  |  |  |  |  |  |  |
| さよなら星 | 谷ゆき子 |  |  |  |  |  |  |  |
| まりもの星 | 谷ゆき子 |  |  |  |  |  |  |  |
| ガラスの靴 | 飛鳥幸子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞子の詩 | 上原きみ子 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lady Love | 小野弥夢 |  |  |  |  |  |  |  |
| フラワー ・フェスティバル | 萩尾望都 |  |  |  |  |  |  |  |
| トウ・シューズ | 水沢めぐみ |  |  |  |  |  |  |  |
| プリマでいこう! | さかたのり子 |  |  |  |  |  |  |  |
昭和の少女たちを魅了したバレエ漫画の世界
記事のポイントをまとめます。
•昭和のバレエ漫画は少女たちの夢と憧憬を捉えた存在であった
•戦後、悲しい母娘ものにバレエ要素が加わり人気を集めた
•初期の作品では困難な状況の主人公がバレエを通して成長する姿が描かれた
•牧美也子の『マキの口笛』は少女漫画における最初のバレエ漫画のヒット作と言える
•バレエのロマンティックなイメージが少女たちの憧れと理想を象徴していた
•谷ゆき子のような超展開なストーリーと美しい絵柄で人気を博す作家も現れた
•少女漫画雑誌「りぼん」では少女たちの夢を育む多くのバレエ作品が掲載された
•山岸凉子の『アラベスク』はバレエの世界の厳しさや美しさ、ダンサーの心理描写を深く描いた
•昭和のバレエ漫画はバレリーナを目指すヒロインたちの内面的な葛藤と成長を描いてきた
•1970年代は情熱と涙が色濃く描かれた物語が多かった
•1980年代には本格的なバレエストーリーに恋愛要素が強く加わる傾向が見られた
•1990年代にはバレエ要素が多様なジャンルの作品に見られるようになった
•昭和のバレエ漫画は少女の夢や憧れを描きながら時代と共に多様な表現を獲得していった
•当時の少女たちの純粋な憧憬が色濃く反映されている点が魅力の一つである
•復刻版によって、かつて少女たちの心を捉えた名作に再び出会うことができる